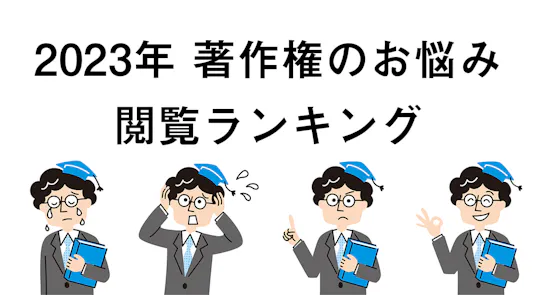著作権Q&A

著作権のお悩みコーナー
お悩み 90|本の紹介で表紙や目次を使っても問題ない?
![]()
本の表紙(書影)を利用する際には、まずは出版社に問い合わせ、著作権者の許諾を取る必要があります。では、目次はどうかというと…
お悩み 89|フィルムコミッションのロケ地情報などで、ロケ風景の写真を使用したい。どこまでが著作物?
![]()
著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条)と定義されています。そのうえで…
お悩み 88|メンバー限定のSNSなら著作物の公開はOK?
![]()
メンバーが限られていても、著作物を利用しているわけですから、著作権者から許諾を得ていなければ違法です。他人の著作物を無条件で公開、共有してもいいという…
お悩み 87|新聞社に許諾を取る方法は?
![]()
許諾を取る際には、新聞社の知的財産権を担当する窓口に、新聞社の定める方法に則って申請します。どの記事を、どのような形で利用するかなどを…
お悩み 86|広告の中の記事は記者が書いた記事と同じ扱い?
![]()
一般の記事の場合、書いた記者個人でなく新聞社や出版社が著作者となるのが基本です。これを「職務著作」(著作権法第15条)といいます…
お悩み 85|著作権表示がないインスタ投稿は転載できる?
![]()
最近はインターネット上のコンテンツに関するご質問が増えてきました。 弊社主催のセミナー(2023年10月)参加者からも「ユーチューバーは広告料を収入源にしているので、著作権の許諾なしで複製は可能でしょうか?」というご質問が寄せられ…
2023年 著作権のお悩みコーナー閲覧ランキング
![]()
お悩みコーナーで回答した内容の中で、2023年に閲覧数が多かったお悩み内容をご紹介いたします。
お悩み 84|ネットニュースのURL紹介は問題ない?
![]()
同様のご質問を頻繁にいただきますが、改めてお答えいたします。 URLの文字列には著作権がありませんので、著作権の観点からは問題ありません。ただし、見出しには著作権がある場合も…
お悩み 83|メディアに掲載されたことを写真付きで紹介したいのですが……
![]()
2人の広報担当者から偶然、似たようなご質問がありましたので、2つまとめてお答えいたします。 自分の会社が新聞や雑誌に掲載されたら「社員に周知したい」「外部にも宣伝したい」と思うのは当然ですよね。その際に著作権に気を配るのも広報担当者としては大事な役目です。 結論から申し上げますと…
お悩み 82|ELNETが提供しているPDFファイルをダウンロードして社内共有することはできるの?
![]()
ユーザーがELNETのシステム上でPDFファイルを閲覧し、印刷することについては、新聞社や出版社から許諾を得ています。しかし、ダウンロードして別途、自社のイントラネットで社員が閲覧できるようにすることは認められていません。 「社内格納」つまり…