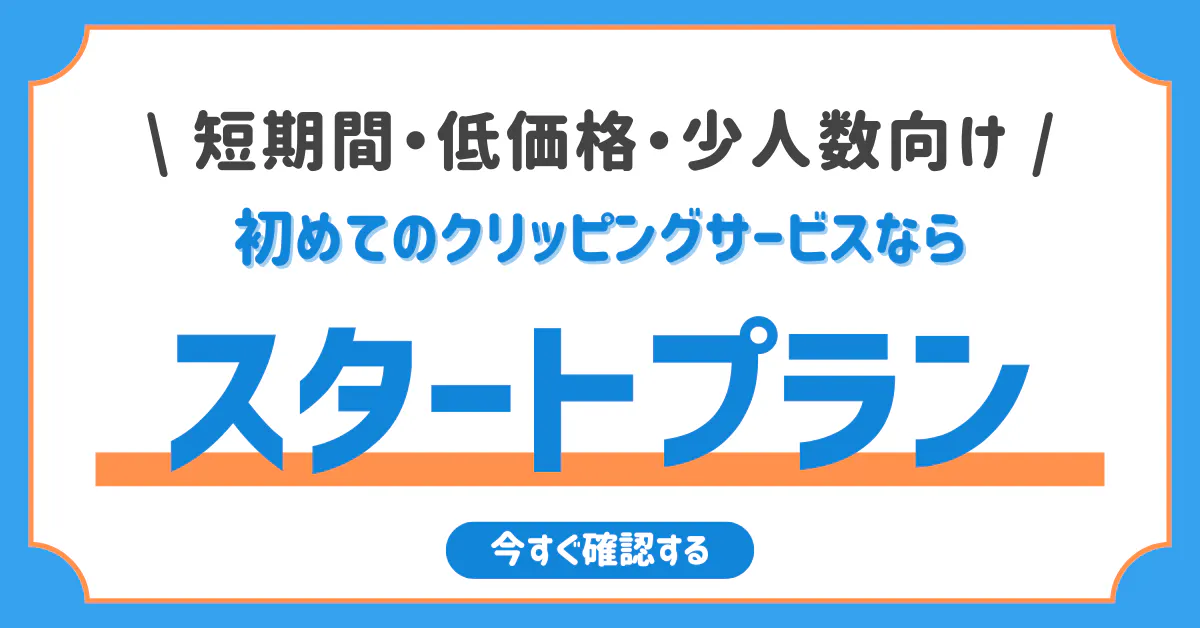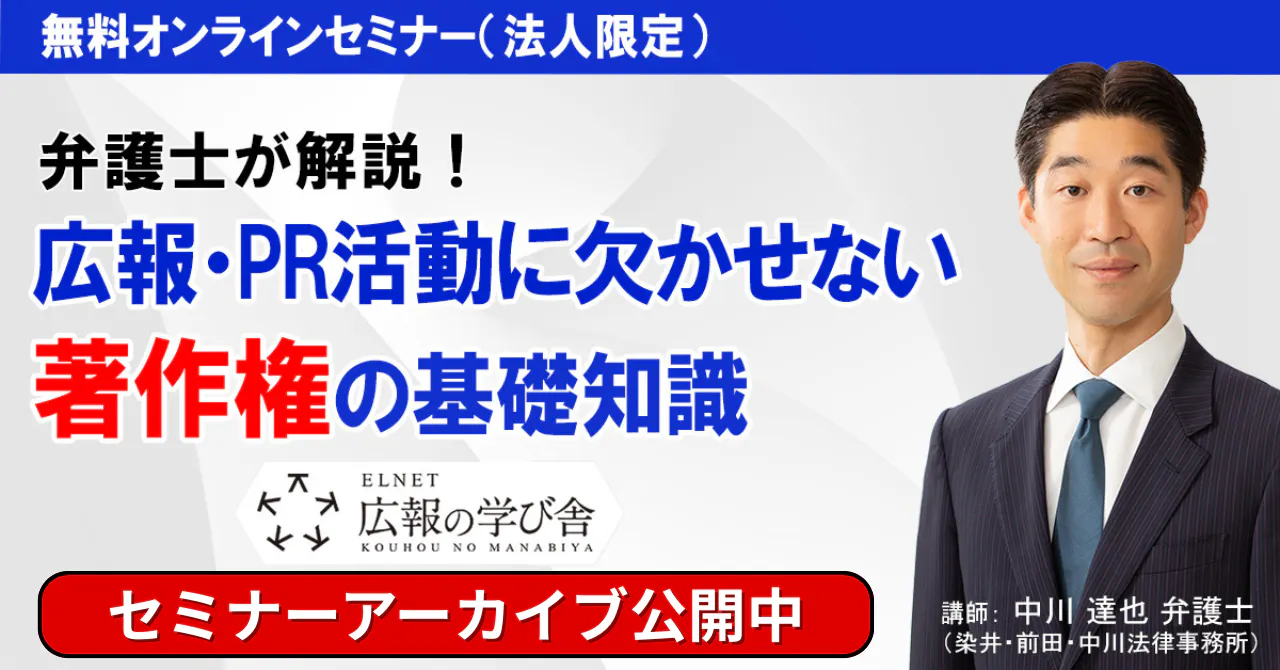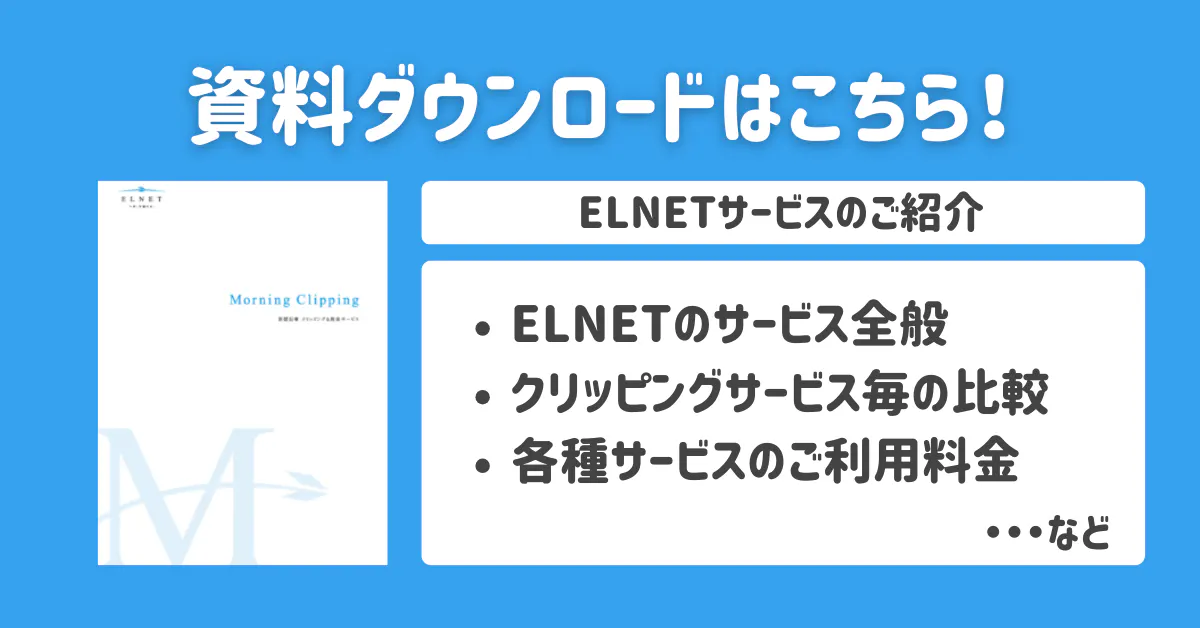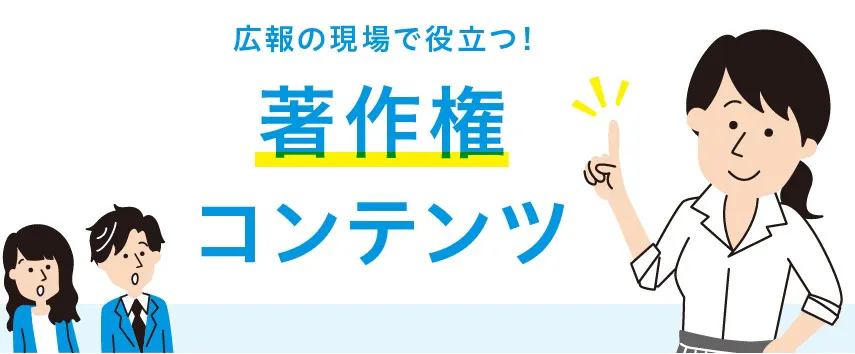【お役立ちコラム】コンプライアンスとは?意味・違反事例・対策をわかりやすく解説

目次
企業の広報担当者にとって、コンプライアンスは理解しておかなければならない事項のひとつです。本記事では、コンプライアンスの基本的な意味から、企業に求められる対応、具体的な違反事例までを解説します。また、違反を防ぐための社内体制の整備や教育の重要性、危機管理広報の役割についても触れ、広報業務で留意すべきポイントを整理します。
コンプライアンスとは?わかりやすく解説
コンプライアンスとは、企業・組織が法令や規則を遵守して、社会的責任を果たすことを指します。
コンプライアンスの意味
コンプライアンスは「法令遵守」という意味で、「コンプラ」と略されることもあります。企業がコンプライアンスを重視する理由は主に2つあります。ひとつは法令を守り、法令違反による事業停止リスクを回避するためです。もうひとつは社会的責任の遂行のためです。企業は利益を追求するだけでなく、得られた利益を社会に還元することで信頼を得られます。コンプライアンスの範囲は、近年、法令だけでなく、倫理・道徳・就業規則などにも広がっています。
企業におけるコンプライアンスの重要性
コンプライアンスは、法的なリスクヘッジに直結し、違反すれば罰金や制裁を受け、企業の信頼を損ねる可能性があります。不正行為があれば、顧客や取引先からの信頼を失い、経営に悪影響を及ぼす恐れがあり、ひいては企業のブランド力・競争力や従業員満足度、モチベーションにも負の影響を与えます。
また、ステークホルダーとの信頼関係の構築は持続的な経営を支えますが、特に投資市場では、コンプライアンスの徹底が企業評価に直結します。
コンプライアンス業務に関わる主な部署
企業のコンプライアンス対応は、一部の専門部署だけで完結するものではありません。各部署がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携することが、より強固なコンプライアンス体制の構築につながります。以下は、各部署のコンプライアンスに関する業務の例です。
- 広報部:社内外への発信を通じて企業の透明性と信頼性を高める。また、不祥事が発生した際には迅速な情報開示と適切な対応を行い、レピュテーションリスクを低減する。
- 総務部:社内規則の整備や従業員向けの教育・研修を実施し、コンプライアンス遵守の意識を 醸成する。
- 経営企画部:経営戦略を策定する際は、コンプライアンスの観点を考慮し信頼性向上を図る。
- 法務部:社内の規程や契約書のチェックを通じて企業の法的リスクを最小限に抑える。また、法的トラブルが発生した際は適切に対応する。
- IR部門:投資家やステークホルダーに対し、正確かつ透明性の高い情報を提供し、企業の健全なガバナンスを維持する。
コンプライアンス違反とは?事例も紹介

企業が法令や社内規則を守らず、倫理的に問題のある行動をとることが「コンプライアンス違反」です。企業の信頼を大きく損ない、社会的な批判や法的措置の対象となる可能性があります。特に広報業務に関連する違反は、企業のブランドイメージを大きく傷つけ、売り上げや事業継続に悪影響を及ぼします。ここでは、広報活動に関わるコンプライアンス違反の事例を紹介します。
誇大広告
誇大広告は一時的に消費者の関心を集め、売り上げ向上につながります。しかし、虚偽などが発覚すれば、企業の信頼が大きく損なわれ、顧客離れのリスクが高まります。特に、SNSの普及によって、消費者の口コミやレビューが拡散しやすくなり、不適切な広告が「炎上」することも多くなりました。広報担当者としては、広告の内容・表現を確認し、消費者に誤解を与えない情報提供を心がけることが重要です。
誇大広告で実際に問題となった事例:
2024年3月、消費者庁は健康食品の通販会社および同社の代表取締役に対して、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止を命じました。同社は、販売する機能性表示食品に関して、「商品を摂取すれば誰でも簡単に痩せられる」といった誇張表現を使用し、あたかも国が認めた効果であるかのように宣伝していましたが、実際にはそのような科学的データはありませんでした。消費者庁はこれを優良誤認表示と判断しました。
さらに、同社は広告表現に「No.1」を使用していましたが、公平・公正な方法で実施された調査に基づいていない点が問題視されました。この事例では、特定商取引法に基づく「著しく事実と相違する表示」が禁止される誇大広告規定も適用されました。
情報漏えい
情報漏えいとは、営業秘密や顧客情報などの企業・組織内部に留めるべき情報が外部に流出することを指し、不正競争防止法や個人情報保護法の規制対象となります。原因には大きく分けて「故意」と「過失」がありますが、多くはサイバー攻撃や不適切な管理が発端となっています。
情報漏えいが発��生すると、企業は社会的信用を損ない、炎上リスクが高まります。特にSNSで拡散されると、消費者の信頼回復には長期的な取り組みが必要になります。適切な広報対応が求められ、透明性を確保しながらの迅速な情報公開と謝罪が必要です。
誇大広告で実際に問題となった事例:
2021年7月、プレスリリースの配信を手がける企業において、公表前のファイル258点が外部からアクセス可能な状態になっていました。これはクラウド上で管理されていたファイルのURLが、類推可能となっていたことが原因でした。この事例では、顧客企業の機密情報が流出し、影響を受けた企業の信頼低下やブランドイメージの毀損につながりました。
著作権法違反
著作権法違反が企業活動においても問題となるケースが少なくありません。特に広報活動では、無断転載や引用が外部とのトラブルを引き起こし、訴訟に発展する可能性があるため、適切な管理が求められます。
企業の広報活動では、記事や画像を引用・共有する機会もありますが、適切なルールを守らなければ著作権法違反となります。過去には、経済ニュースなどを配信する企業が新聞社の記事を無断転載し、訴訟問題に発展した事例がありました。これは、企業のコンテンツ活用におけるリスクを浮き彫りにしました。
無断で新聞記事をコピー・配布する行為は著作権法違反となりますが、信頼できるクリッピングサービスを活用すれば、適切な許可を得たコンテンツを安心して利用できます。クリッピングサービスは、新聞や雑誌などの掲載記事を、著作権を遵守した形で収集・提供するサービスで、企業の情報収集に役立ちます。ELNET(イーエルネット)ではさまざまなニーズに応えるクリッピングサービスを提供しています。
このほかにも社内研修を実施して従業員の意識を高めたり、ライセンス契約を締結してただしくコンテンツを活用したりすることで、著作権法違反のリスクを回避できます。
不適切なSNS投稿
不適切なSNS投稿は、企業のブランドイメージを大きく損ねるリスクを伴います。SNSは広範囲かつ迅速に情報が拡散されるため、一度炎上すると収束に時間と労力がかかり、場合によっては企業の信用度が大きく低下します。
SNSにおける誤った発信や不適切な内容は、顧客や消費者からの反感を買い、炎上を引き起こすことがあります。こうしたコメントが投稿された場合には、迅速に対策を講じる必要があります。
不適切なSNS投稿で実際に問題となった事例:
清涼飲料水メーカーがSNS投稿で炎上したケースがあります。この事例では、商品とともに描かれた女性のイラストや文言が不快に感じるという声が多く集まったことを受け、同社は投稿内容�の削除と謝罪を速やかに行い、炎上を最小限に食い止めることができました。
コンプライアンス違反を起こさないための対策とは?

企業がコンプライアンス違反を防ぎ、健全な経営を維持するためには、日常的な取り組みと対策が不可欠です。ここでは、コンプライアンス違反を未然に防ぐための具体的な対策について解説します。
社内体制の整備
コンプライアンス違反を防ぐためには、まず社内のコンプライアンス体制を整えることが必要です。コンプライアンスに関する規程やルールを明確にし、全従業員への周知を徹底することが、違反を未然に防ぐための第一歩です。
コンプライアンス教育の実施
コンプライアンス教育は、組織内でのコンプライアンスへの意識を高め、違反リスクの低減につながります。
教育では過去の違反事例を用い、社員にリスクを認識させるとともに、実際に発生し得るシナリオをシミュレーションし、当事者意識を高めると効果的です。特に新入社員には、法令や企業規則、情報の取り扱い方法、SNSの使い方など、基本的なコンプライアンスに関する教育を行うことで、リスクを避けるための基礎を早期に築けます。
相談窓口の設置
相談窓口を通じて、社員が不正や不祥事を躊躇(ちゅうちょ)なく報告できるようにすれば、問題の早期解決につなげられます。
通報窓口は、内部通報窓口だけでなく、外部の専門機関に委託する方法もあります。外部に窓口があることで、通報者の匿名性やプライバシーが確保され、企業内部での報復や圧力を防ぐことができ、従業員が安心して通報しやすくなります。さらに、外部委託によって、通報内容が第三者により公正に扱われるため、企業の透明性が保たれ、信頼性を高めることにもつながります。
加えて、外部ホットラインサービスを活用することで、通報受付の運営がより効率的かつ専門的に行えるため、企業にとっては負担が軽減されます。
情報のキャッチアップ
法律や規制に関する最新情報を常にキャッチアップすることも欠かせません。新たな法律の制定や法改正に対する迅速な対応は、企業の法的リスクを低減し、不祥事を未然に防ぐための重要なステップです。
コンプライアンス体制を強化するには、定期的に法令や規制の最新情報を把握する仕組みを整えることが重要です。例えば、法律に関するセミナーや勉強会を開催したり、最新の法改正を自動で通知してくれるツールを導入して効率的に情報収集したりする方法があります。
コンプライアンスに関わる広報の役割―危機管理広報
広報部門は、危機管理広報を通じて、企業の信頼性を守り、損なわれたイメージを回復するための施策を実施します。
危機管理広報とは
危機管理広報とは、企業が不祥事や事故、製品リコール、情報漏えい、サイバー攻撃などの突発的な危機に直面した際に、その影響を最小限に抑え、企業の信頼を守るために行う広報活動のことです。危機発生時には適切な情報発信が求められ、対応を誤ると企業の評判が大きく損なわれる可能性があります。
危機管理広報の役割は大きく3つに分かれます。第一に、潜在的なリスクを予測し、未然に防ぐことです。業界動向の分析や社内コンプライアンス強化を通じて、危機の発生を抑えることが重要になります。
第二に、危機発生時の迅速な情報開示と適切な対応です。事実を正確に伝え、関係者への説明責任を果たすことで、不必要な誤解や憶測を防ぎます。
第三に、風評被害の最小化と信頼回復です。危機後の対応次第で、企業のイメージが大きく変わります。誤った対応が続けば長期的にブランド価値を損なう可能性がありますが、適切な広報を実施すれば信頼を取り戻し、企業の存続と社会的評価を守ることもできます。
なぜ危機管理広報が求められるようになったのか?
危機管理広報が求められるようになった背景には、いくつかの重要な要因があります。なかでもインターネットの普及とSNSの台頭が大きな影響を与えています。
・急速な情報の拡散
インターネットが利用されるようになったことで、情報の拡散スピードが飛躍的に上がりました。企業は迅速かつ適切に対応しなければ、批判や炎上が拡大し、企業の信頼が大きく損なわれるリスクがあります。
・法令や規制の強化
法令や規制が厳しくなるなかで、企業はコンプライアンス違反に対する迅速な対応が求められます。適切に対応しなければ、法的制裁や経済的損失が発生する可能性が高まります。危機管理広報を通じて、企業は法令や規制に適切に対応し、リスクを最小限に抑えられます。
・企業の信頼性とブランド価値の保護
企業が危機的な状況に直面しても、適切な危機管理広報を行えば信頼性とブランド価値を保護できます。迅速な情報収集と分析、適切な対応策の実施、効果的なコミュニケーション戦略を展開することで、被害を最小限に抑え、企業の将来に与える影響を軽減します。
まとめ
コンプライアンス違反は誇大広告や情報漏えいなど多岐にわたり、企業の信用度が大きく低下する可能性があります。コンプライアンスを徹底するためには、社内体制の整備や教育の実施が求められます。さらに、インターネットの普及により、危機管理広報も重要視されています。適切に対応し、社会からの信頼を維持すれば、企業の持続的な成長が期待できます。
以下の資料で著作権について詳しく説明しています。
下記フォームからダウンロードいただけますので、フォームに必要事項を入力し、お気軽に送信ください。

※本コラムはELNET外部の筆者が執筆しています。