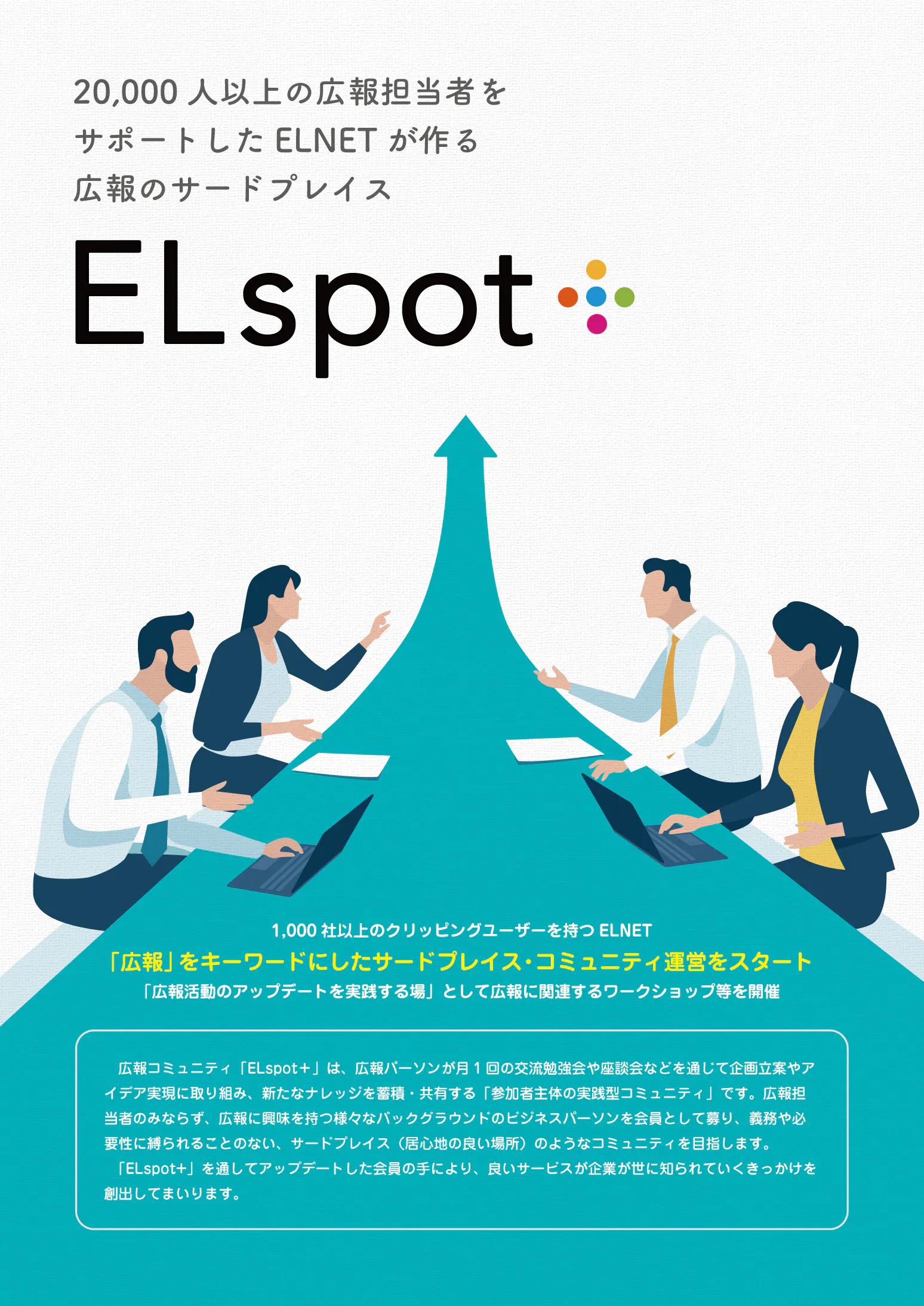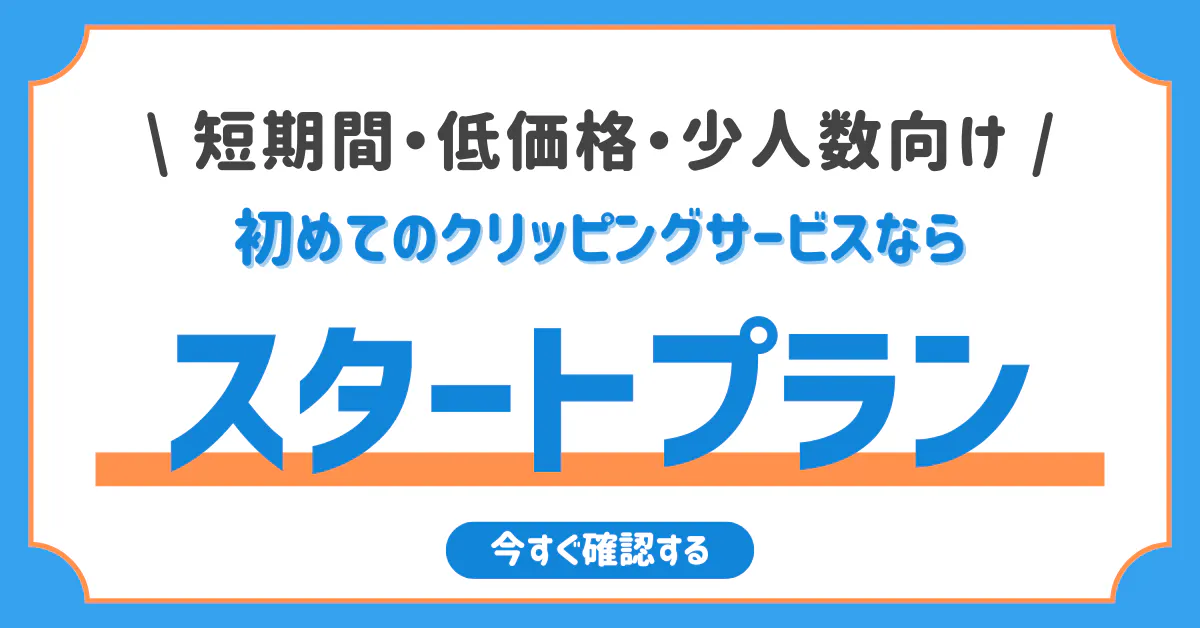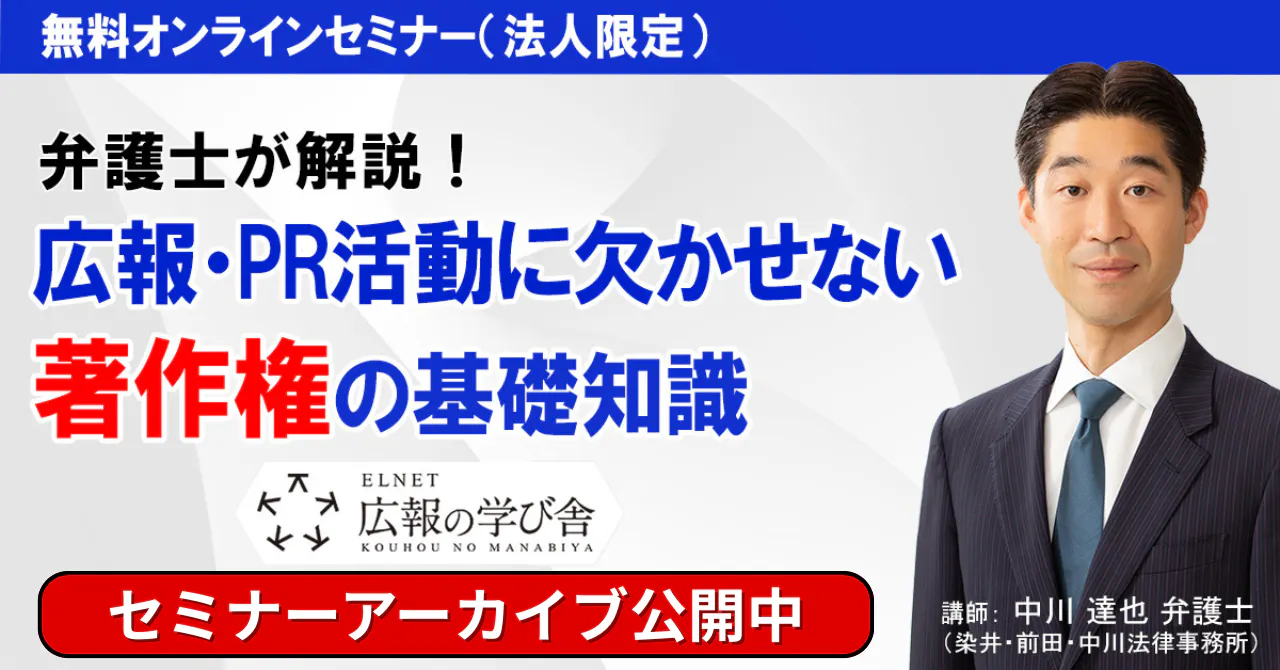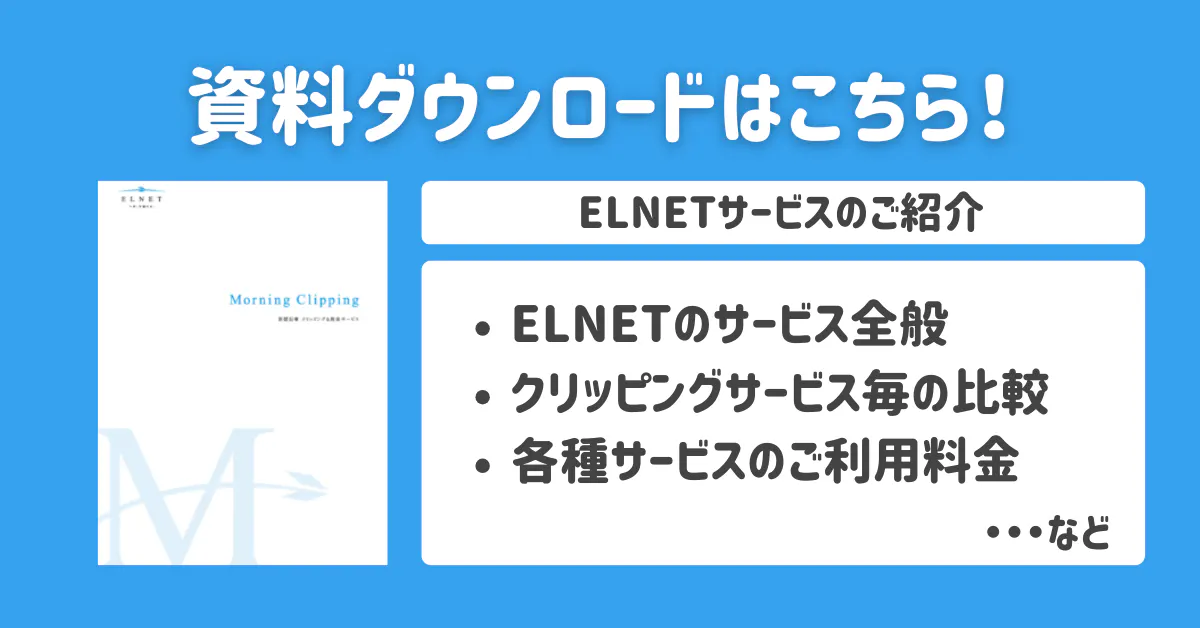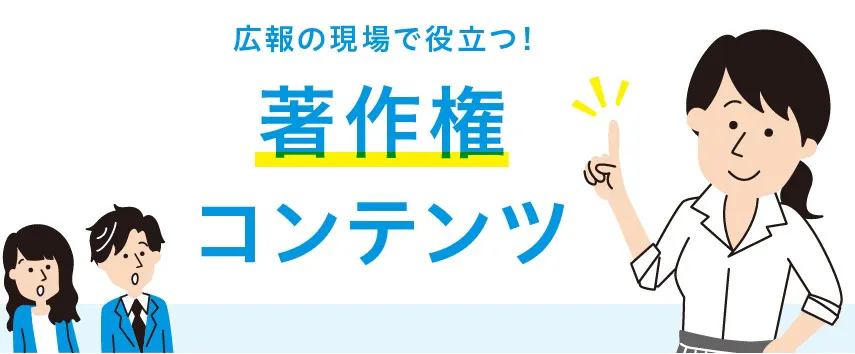【ELspot+】 『“選ばれる会社”になるための採用広報戦略~面接率・内定承諾率を高める「伝え方」の仕組み化~』

【本日の流れ】
1:レクチャー:「“選ばれる会社”になるための採用広報戦略 ~面接率・内定承諾率を高める『伝え方』の仕組み化~」
ゲスト講師:斉藤 久良良 氏
(株式会社プラスカラー 取締役COO・広報コンサルタント)
2:グループワーク&ディスカッション
3:参加者の感想
【背景】
少子高齢化や求職者の価値観の多様化が進み、企業の人材確保はますます難しくなっています。またそれに伴い、採用プロセスも変化し、採用チャネルも多角化しています。
このような状況下では、企業は自社の魅力や独自性を積極的に発信することで、多くの競合の中から自社を選んでもらうことが必須になります。そのため、従来の応募を待つだけの「待ち」の採用活動ではなく、求職者に対して積極的に働きかけていく「攻め」の“採用広報戦略”が必要になっているのです。
そこで、9月のELspot+では、「“選ばれる会社”になるための採用広報戦略~面接率・内定承諾率を高める『伝え方』の仕組み化~」をテーマとして、採用難時代における新たな採用広報戦略についての交流勉強会を開催しました。講師は、20年にわたり多くの企業広報を支援してきた斉藤久良良氏(株式会社プラスカラー 取締役COO・広報コンサルタント)をお招きしました。
前半のレクチャーでは、斉藤氏より、採用広報戦略が必要な背景、採用広報を進めるステップ、押さえておくべき重要ポイントなどについて解説いただきました。後半では、レクチャー内容を踏まえて、グループワーク&ディスカッションを行いました。
本レポートでは、レクチャーおよびグループワーク&ディスカッションの内容、参加者の方々の感想をお届けします。
【本日の交流勉強会】
1:レクチャー:「“選ばれる会社”になるための採用広報戦略」(斉藤 久良良 氏)
ゲスト講師:斉藤 久良良 氏(株式会社プラスカラー 取締役COO・広報コンサルタント)
https://pluscolor.co.jp/about/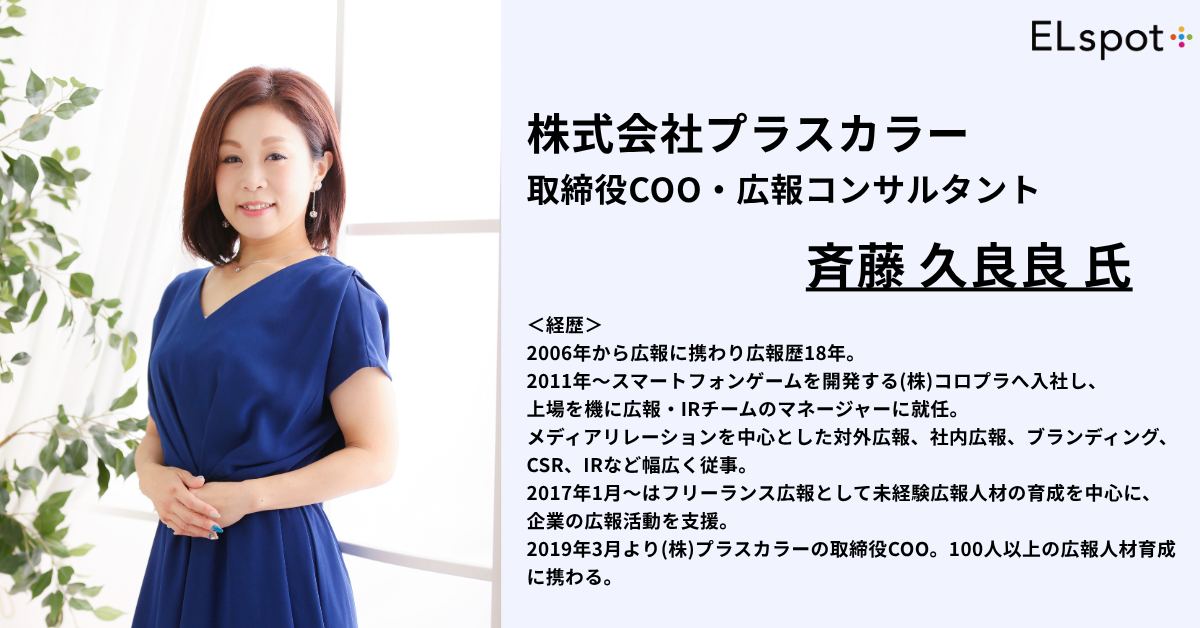
【主な内容】
1 採用広報戦略が必要になった4つの時代背景
「なぜいま、採用広報が必要なのか?」について、斉藤氏は次の4点を挙げました。
①人手不足による「超売り手市場」化:
・深刻な人手不足により、採用市場が「超売り手市場」になっており、母集団(自社の求人に興味を示し、応募してくれる求職者群)形成がますます困難になっている。
②採用活動プロセス(責任領域)の拡大:
・採用活動で行うべき領域が、従来の「募集・選考・採用」だけでなく、募集以前の「自社の認知・興味向上」や、入社後の「定着促進」にまで拡大した。
③採用手法(採用チャネル)の多様化:
・かつては求人媒体への掲載が主流だったが、現在では人材紹介・スカウト、SNSを活用したソーシャルリクルーティング、社員によるリファラル採用など、さまざまな手法を組み合わせることが求められている。
④求職者の行動変化:
・求職者も企業のリアルな姿を知るために、求人情報だけでなく、企業のホームページや口コミサイトなどで事前に情報収集を積極的に行うようになった。
▶これらの環境変化に対応するためには、現在、就職や転職を考えている『顕在層』だけでなく、まだ就職・転職を考えていない『潜在層』にも、企業の“ありのままの魅力”を届ける『採用広報戦略』が不可欠になる
2 採用広報を効果的に進めるための3つのステップ
「採用広報は単なる情報発信ではない。戦略的に設計し、企業の魅力や価値を伝える必要がある。そのためには、次の3つのステップが重要となる」と斉藤氏は言います。
ステップ①:誰に伝えるか(“ターゲット”の明確化)
・誰にその情報を伝えたいのかを具体的に設定する。
・「全員に届けたい」という考えは、結局、誰にも響かない結果になる。
ステップ②:何を伝えるか(伝える“切り口”の作成)
・求職者が“共感”できるかが重要。
・社員の雰囲気や働き方、仕事のやりがいなど、自社ならではのストーリーとして伝える。
ステップ③:どう伝えるか(届ける“手段”の設計)
・求人サイト、採用ホームページ、SNS、口コミサイトなど、情報を届ける手段を検討する。
・一度きりの発信だけでなく、継続的に更新・発信することが信頼構築につながる。
3 採用広報で押さえるべき3つのポイント
採用広報活動を進める上で特に重要となるポイントとして、下記の点を斉藤氏は挙げました。
ポイント①:採用活動の各段階で起こる課題を整理して、有効な情報を発信する
・認知段階:SNSや採用サイトで社員の日常、イベントの様子を伝える。
・興味/応募段階:オウンドメディアで社員インタビュー、職場紹介、開発ストーリーを伝える。
・面接/内定承諾段階:代表メッセージ動画や選考プロセスを解説したコンテンツを伝える。
ポイント②:求職者が気になること、知りたいことを意識して発信する(4つのP)
・Philosophy(理念・目的):会社のビジョン、経営理念・目的
・People(働く人):会社の雰囲気、カルチャー
・Profession(仕事・事業):事業内容、仕事のやりがい、開発ストーリー
・Privilege(待遇・条件):働き方、給与制度、福利厚生
▶中でも、消費行動が自分の共感した「人」に紐づく「ヒト消費」へと変化している現代においては、誰と働けるか、誰がどのような苦労を乗り越えその事業を始めたかといった「People(働く人)」にフォーカスしたコンテンツが効果的。
ポイント③:複数のメディアを組み合わせて、多角的に情報を届ける(PESOモデル)
・Paid Media(有料広告): 認知拡大・集客増加を図る
・Earned Media(口コミ・レビュー、記事):第三者からの評価や信頼を得る
・Shared Media(SNS):求職者からの共感や拡散を狙う
・Owned Media(オウンドメディア):自社の魅力を自由に発信し、ブランドを構築する
▶これら4つのメディアを連携させることで相乗効果を生み出す。
たとえば、採用サイト(Owned Media)に掲載したインタビューを SNS(Shared Media)で拡散し、マスメディア(Earned Media)に記事にしてもらうことで、多角的に自社の魅力を発信することができる。
4 メディアを活用した採用広報の成功事例
上記のポイントを踏まえて優れた採用広報戦略を実践している事例を紹介いただきました。
Owned Mediaを活用することで、自分たちの魅力を自分たちで発信している事例
・ナイル株式会社:https://nyle.co.jp/recruit/career/
マスメディアをEarned Mediaとして活用し、採用活動につなげている事例
・サイバーエージェントほか:https://mainichi.jp/bossmeshi/
Shared Mediaをフル活用・連携させ、社員の個の発信力を強化している事例
・株式会社LayerX:https://jobs.layerx.co.jp/
5 ストーリーを活用した採用広報事例
最後に、ストーリーを活用し、「社員の生の声」を発信することで共感度upにつなげている効果的な事例を紹介いただきました。
・NOZOKIMI(プラスカラー):https://nozokimi.jp/
※「女性」の働き方に特化したサイトのため特定のターゲットにリーチしやすい。
2025年6月にリニューアルし、子育て世代が「自分らしく働ける場所=適材適所」を見つけられる情報発信を目的に、柔軟な働き方を実現する企業の取り組みを、社員インタビューを通して紹介している。
2:グループワーク&ディスカッション
レクチャーの内容を踏まえ、下記の課題を抱える企業事例の改善ポイント、解決施策について、グループに分かれてディスカッションをしました。
テーマ:「あなたなら、採用広報戦略を検討する上で、どの課題に着目し、どのような解決施策を実施しますか?」
《事例:ある企業における課題》
課題①:「母集団人数」が年々減少している
課題②:説明会から「選考への参加率」が3年前から10%以上ダウンしている
課題③:「内定承諾率」が40%強
課題④:3年後の「定着率」が7割程度(3割離職)
《主なディスカッション内容》
①「母集団形成」に着目したグループ:
・母集団形成にあたっては、専攻などターゲットを絞ったアプローチをすることが重要。
・それにより、「有効母集団」(自社に強い興味・関心を持つ層、自社が必要とするスキルを持つ層)を見極め、その層が検索するであろうキーワードを自社のHPやオウンドメディアに埋め込む。
②「選考への参加率」に着目したグループ:
・「人の魅力」を伝えることが重要だとは分かっているが、メディアに出ることが苦手な社員が多いことが課題……。
・広報担当者も説明会に参加し、人事の採用担当者と同じ目線で現場感覚を共有することが重要。
③「内定承諾率」に着目したグループ:
・辞退理由や辞退後の進路分析に基づき、自社の魅力のアピールポイントを再検討する必要がある。
・ある企業では、あえて選考プロセスを長くする(面接ステップを増やす)ことにより内定承諾率を高めているという。逆転の発想で学びになった。
④「定着率」に着目したグループ:
・定着率が高ければ、採用する必要もない。その意味では、定着率は重要。
・しかし、「定着率の高さ」が必ずしも企業の魅力になるわけではないのではないか。たとえば、「定着率3割」は、「3年で成長できて羽ばたける会社」というように、見せ方次第でポジティブポイントになるのではないか。
3:参加者の感想
今回の交流勉強会の参加者からは、次のような感想がありました。
- 採用広報についてどこから手を付けようか迷っていたため、具体的なプロセスを学ぶことができ実践に役立てそうです。
- 人事(採用)担当者の課題・悩みを聞くことができて、学びになりました。広報担当者として、普段から人事と連携し問題意識を共有していかなければいけないと感じました。
- グループワークがあったことで他社の広報の方とコミュニケーションを取ることができ、貴重な機会となりました。
- 他社の状況を知ることで自社の立ち位置を確認することができ、有意義な時間でした。