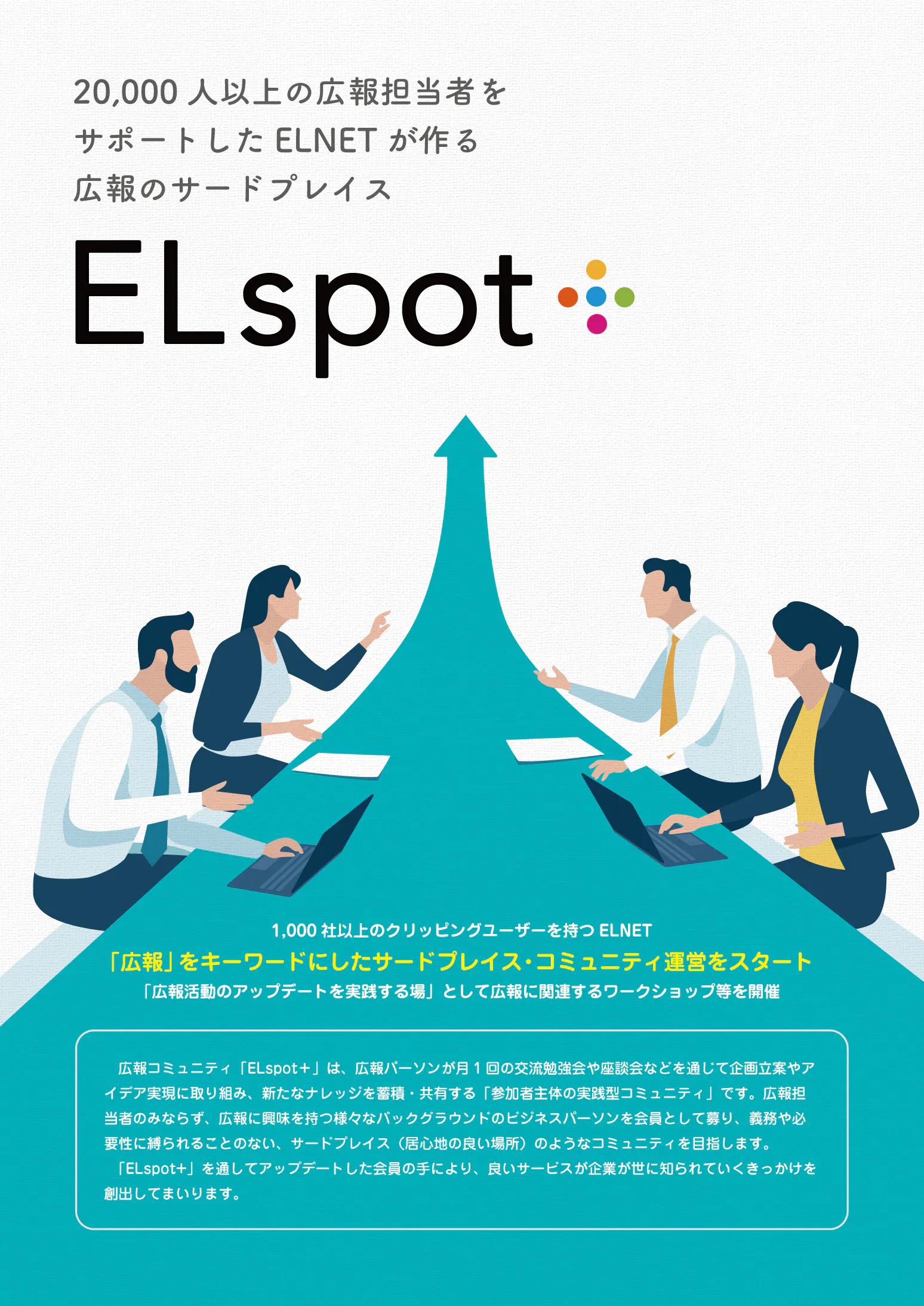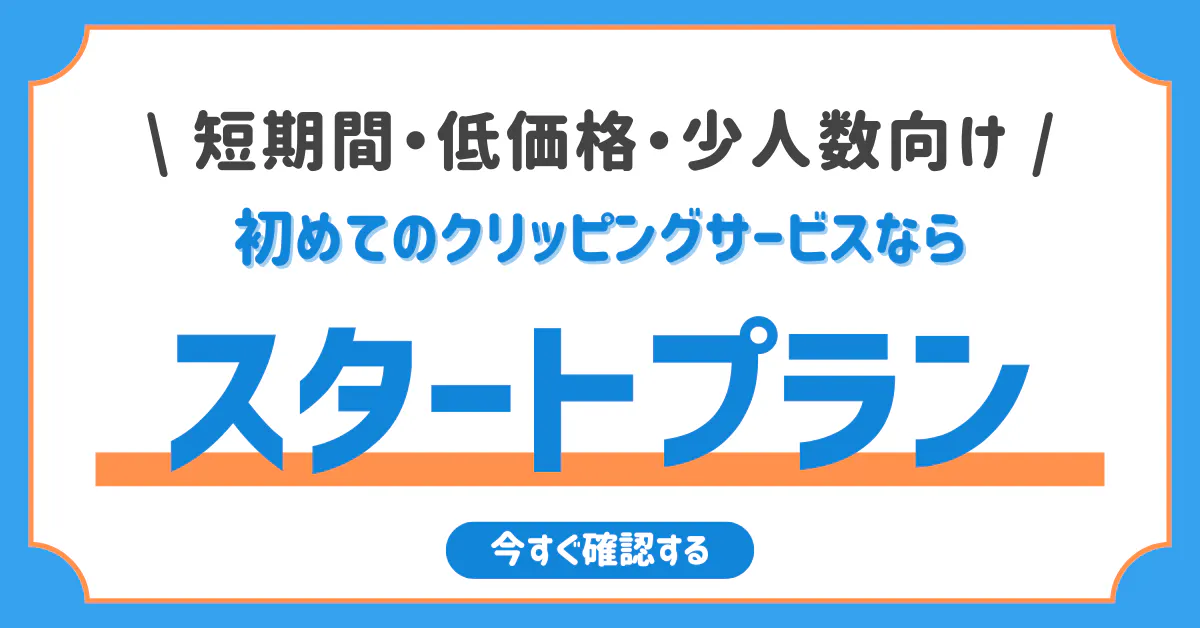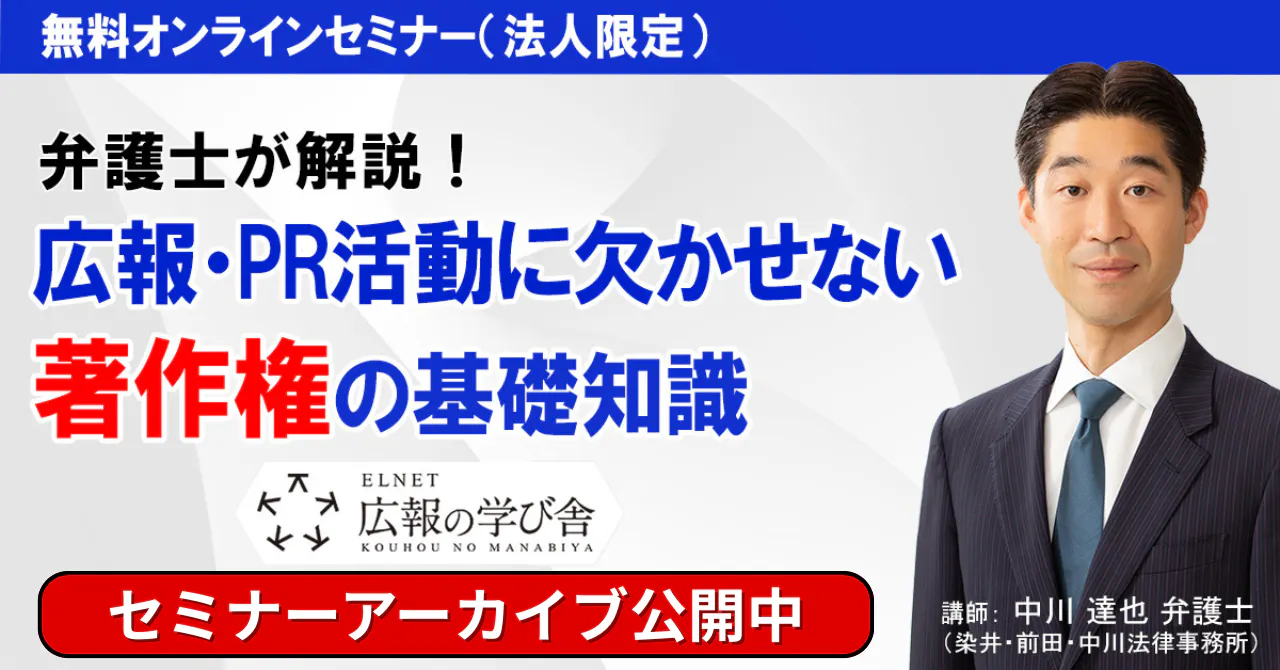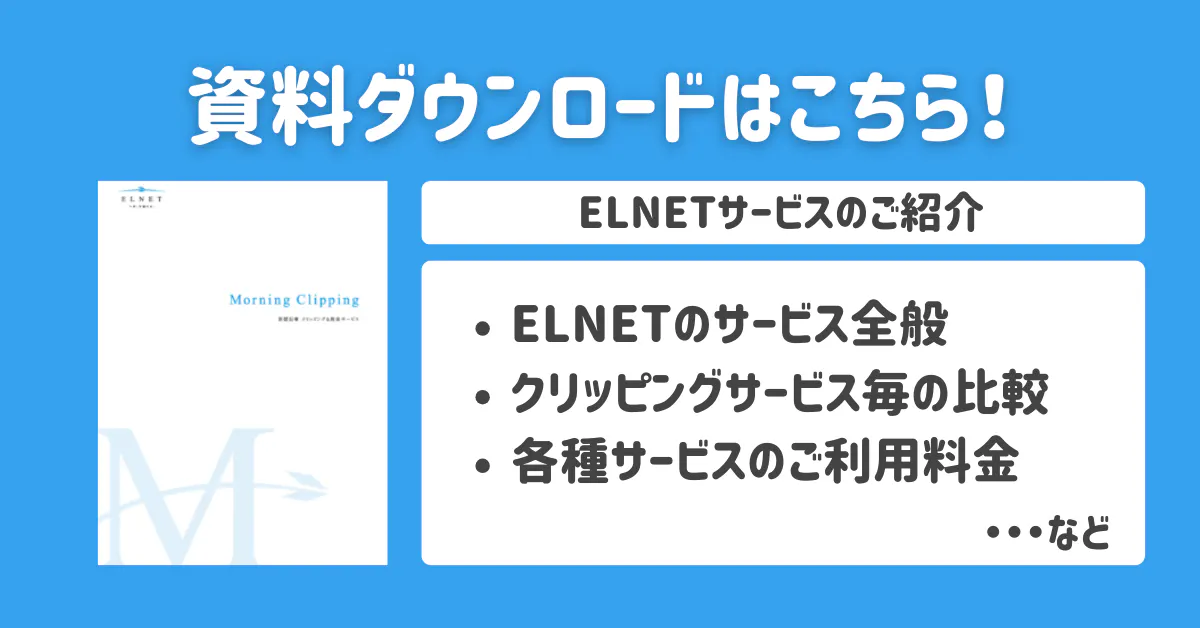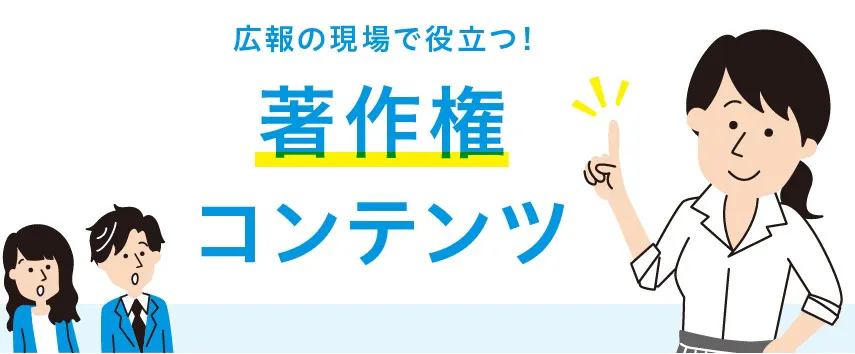【ELspot+】 『“生きた”企業発信力とはなにか?~明日から使えるオウンド運用実践ノウハウ~』
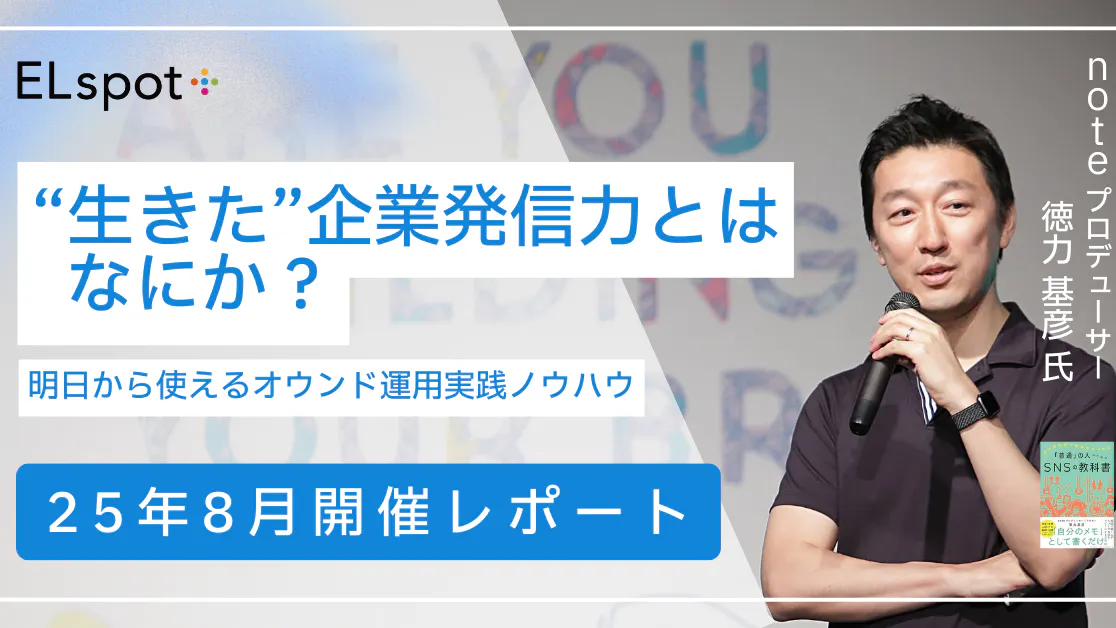
【本日の流れ】
1:レクチャー:「“生きた”企業発信力とはなにか?」
ゲスト講師:徳力 基彦 氏
(note株式会社 noteプロデューサー/ブロガー)
2:参加者の感想
【背景】
SNS(ソーシャルメディア)やオウンドメディアを活用した企業のコミュニケーション強化やブランド価値向上の取り組みが活発化しています。
SNSやオウンドメディアは、単なる情報発信ツールではなく、顧客との信頼関係を築き、ブランド価値を高めるための「資産」となります。そのためには、どのようなSNS活用、どのようなオウンドメディア運用が有効なのでしょうか。どうすれば、“生きた発信”を行うことができるのでしょうか――。
ELspot+では、7月~8月の2か月間に渡り、「SNS活用」をテーマにした交流勉強会を開催しました。7月は「SNS運用の第一歩」として、情報発信の重要性や注意点を基礎から学びました。8月はその学びをさらに一歩進め、「企業として、どう発信していけばいいか」という実践面に焦点を当てました。講師は、いずれも、「noteプロデューサー/ブロガー」として多くのビジネスパーソンや企業におけるSNS活用をサポートしている、note株式会社の徳力基彦氏です。
8月のテーマは、「“生きた”企業発信力とはなにか?~明日から使えるオウンド運用実践ノウハウ~」です。前半のレクチャーでは、オウンドメディアの運用実践として「noteを活用した情報発信の基本と事例」をご紹介いただいた上で、「企業の情報発信の実践ステップ」を解説いただきました。後半では、レクチャー内容を踏まえ、参加者からの感想発表を行いました。
本レポートでは、レクチャーの概要、および、参加者の方々の感想をお届けします。
【本日の交流勉強会】
1:レクチャー:「“生きた”企業発信力とはなにか?」(徳力 基彦 氏)
ゲスト講師:徳力 基彦 氏(note株式会社 noteプロデューサー/ブロガー)
https://note.com/tokuriki
【主な内容】
1 大事なことは、情報発信の「ターゲット」を間違えないこと
- オウンドメディアで情報発信する際に最も重要なことは、「ターゲット」の設定である。
- 最初から新規顧客を狙うのではなく、まずは「コアファン(既存顧客)」をターゲットとすべき。
- 新規顧客にいきなり情報を届けるのは難しい。宣伝色の強いコンテンツは読んでもらえない。
- 「コアファン」は企業の情報をSNSで拡散してくれる。
- 既存顧客(コアファン)を喜ばせるコンテンツが、結果的に、新規顧客に届く。
2 noteによる情報発信の特徴・効果
- noteはどのような分野に有効か?
①採用広報/②B to Cブランディング/③B to Bブランディング
- 効果的なコンテンツは?
「先輩社員の生の声」「会社の空気感が伝わるもの」「採用面接でいつも話すこと」「誰も知らない業界ノウハウ・お役立ち情報」「顧客のサクセスストーリー」などなど。
- noteで発信することにより、どのような効果があったか?
「就職応募者が3倍になった」「社員の個性発信で指名発注を獲得できた」「新規問い合わせを獲得できた」「既存顧客や社員の会社愛着度が向上した」「顧客やステークホルダーに自社の想いが浸透した」などなど。
- note pro(有料版)でできること
「充実したカスタマーサポート」「強固なセキュリティ機能、分かりやすい解析ツール」など。
3 noteによる情報発信を成功させるための秘訣
企業情報を発信する「メディア」には、3つの種類がある
- ①オウンド(Owned)メディア:自社でコントロールできるメディア
- ②ぺイド(Paid)メディア:広告など、お金を払って使うメディア
- ③アーンド(Earned)メディア:SNSなど、評判や口コミが拡散されるメディア
- → 各メディアの特徴を理解し、連携させて活用することが成功の鍵となる。
オウンドメディアは、「メディア」(広告・宣伝)ではなく「コミュニケーション」である。
- 「メディア」と捉えると、「質の高い、完璧な文章を書かないといけない」と思ってしまう。
- 「会社が発信したい情報」と「読者が読みたい情報」には、ギャップがある。
- 「コミュニケーション」なのだから、文章力はいらない。「メモ」「手紙」レベルでOK。「質より量」を狙う。
オウンドメディアは、「プッシュ型コミュニケーション」(相手を決めて返事を求める)ではなく、「プル型コミュニケーション」(よければ読んでね、と強制しない)である。
- noteは、「広告」(バナー)がないことが特徴(自社に関係のない広告が出ない)。
4 企業のオウンドメディアとしての「note活用の5つのステップ」
ステップ①:まずは、個人で練習する
- 個人で「講演メモ」「読書メモ」「ニュースメモ」を作成・発信(アウトプット)する。
ステップ②:次に、メールにnote記事を+α(添付)する
- メールに「自己プロフィール」「商品やサービスへの想い」「ちょっとした仕事のノウハウ」などを添付して、話題を広げ、印象を深める。
ステップ③:オープン社内報(社外の人も読める社内報)を作る
- 社員が読んで面白いと思う記事は、社外の人も面白いはず。
- 「社内のユニークな取り組みの舞台裏」「社員の生の声」「我が社のちょっとした仕事のノウハウ」などを社外に向けて発信する。
- noteは「ストーリー」を伝えるプラットフォームである。
- 「社員の書いたnote」を会社のnoteで発信すると、社員の生の姿が伝わり、社員の顔が見える。また、そのことにより、社員を巻き込み、情報発信する仲間を増やすことができる。
ステップ④:オンライン接客のツールとして活用する
- note記事を、一人の顧客と会話・接客している感覚で書く。
- 例えば、「商品やサービスの開発ストーリー」「顧客事例インタビュー」などを、目の前にいる顧客に直接説明するイメージで書く。
- 「顧客の書いたnote」を会社のnoteで発信すると、顧客の生の声が伝わる。
ステップ⑤:上記のステップの後に、「企業のメディア」になる
- コミュニケーションにより「コンテンツ」(記事)が蓄積されると、その結果、「メディア」(広告・宣伝)になる。
- メルマガや公式SNSアカウントで紹介する。その際、「検索経由でのアクセス獲得」を意識することが重要。
5 オウンドメディアの「効果測定」の考え方
- noteを活用したオウンドメディアは、広告とは異なり、「心を動かすコミュニケーション」である。
そのため、短期的な数値で成否を判断するのではなく、長期的な視点を持ち、継続して取り組むことが成功の秘訣。
- 重視すべきKPI:
定性的評価:読んだ人の「心の動き」を重視。面接や商談で「どの記事が記憶に残っていますか?」と聞く。
定量的評価:単月のページビューではなく、累積ページビュー(「年間で何人とコミュニケーションできたか」など)を意識する。それにより、継続的な積み上げを評価でき、担当者のモチベーション維持につながる。
6 さいごに
- noteを活用したオウンドメディアとしての価値は、「広告」ではなく、「会話」(コミュニケーション)、「接客」である。
- 成功の最大の秘訣は、「継続すること」。そうすれば、必ずストック(累積効果)が効いてくる。
2:参加者の感想
レクチャーを聞いて、参加者から次のような感想がありました。
- 「オウンドメディア」については、これから踏み出そうとしているところだったので、目指す方向が見えて、踏み出す一歩になりました。
- 「メディア」の種類や捉え方、それぞれの長所・短所について学ぶことができ、オウンドメディア実践へのハードルが下がりました。少し気軽に始められそうです。
- 「noteを活用したオウンドメディア」について、分からないことが多かったため、今日のレクチャーで具体的な進め方、成功事例を教えていただき、noteに対する理解が深まりました。
- 広報として情報発信する際は、「会社を代表しているのだから、間違えてはいけない」と思っていましたが、「SNSはメディアではなく、おしゃべり(コミュニケーション)である」というお話を聞き、気が楽になりました。
- 「オウンドメディア」として発信するのは、企業の公式情報(=A面情報)だけでなく、社員のカジュアルな(本音の)情報(=B面情報)が重要であると理解できました。
- オウンドメディアの「効果測定」をする上では、「定量評価」(=ページビューの多さ)よりも「定性評価」(=心をどれだけ動かせたか)が重要という視点は、とても参考になりました。
- 「オープン社内報」は、オウンドメディアを始める上で良いきっかけになりそうです。実践したいと思います。
- オウンドメディアを始めるにあたり「社内をどう説得すればいいか」と悩んでいましたが、その解決策を教えていただき大変参考になりました。早速、社内でトライしてみたいと思います。