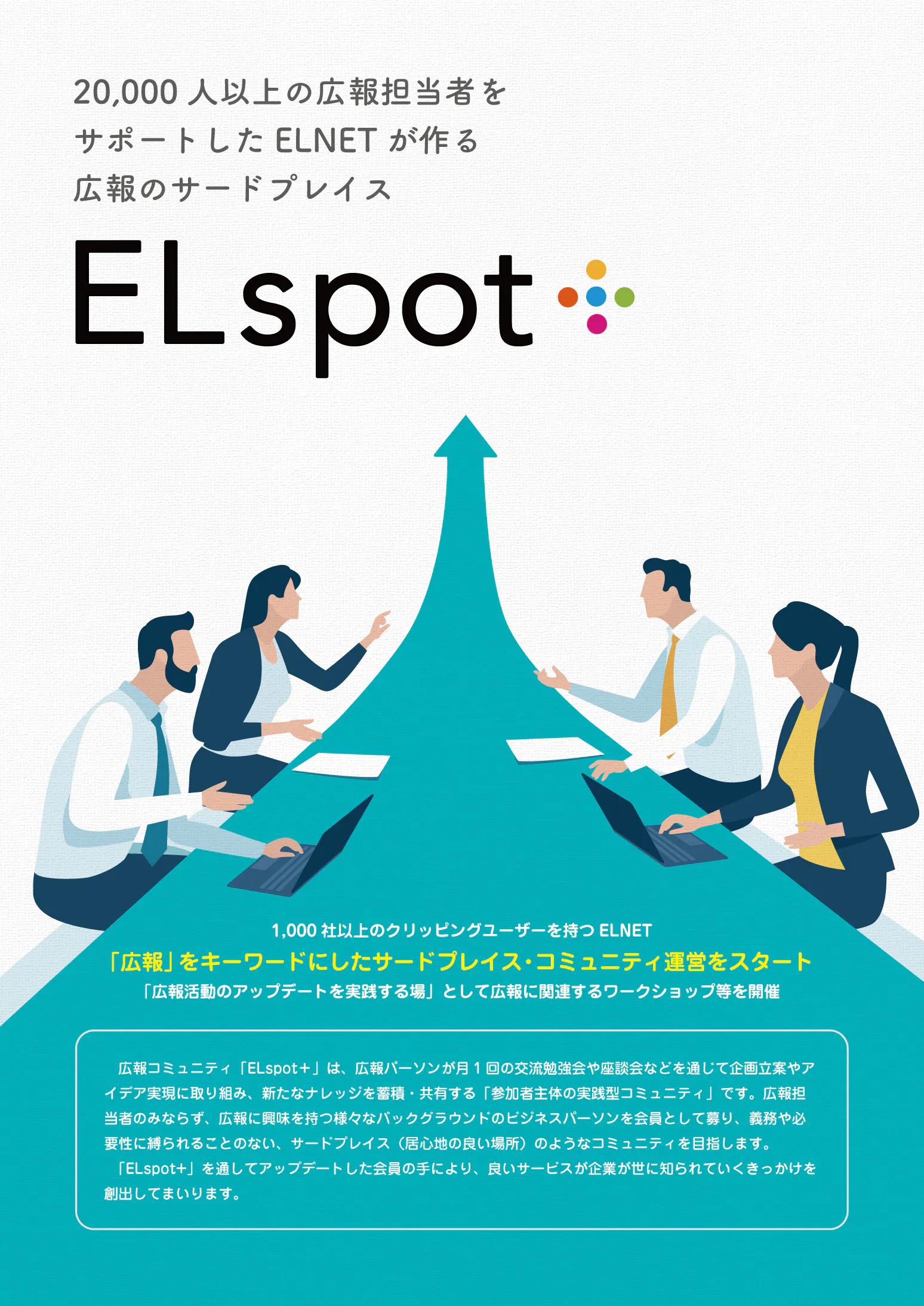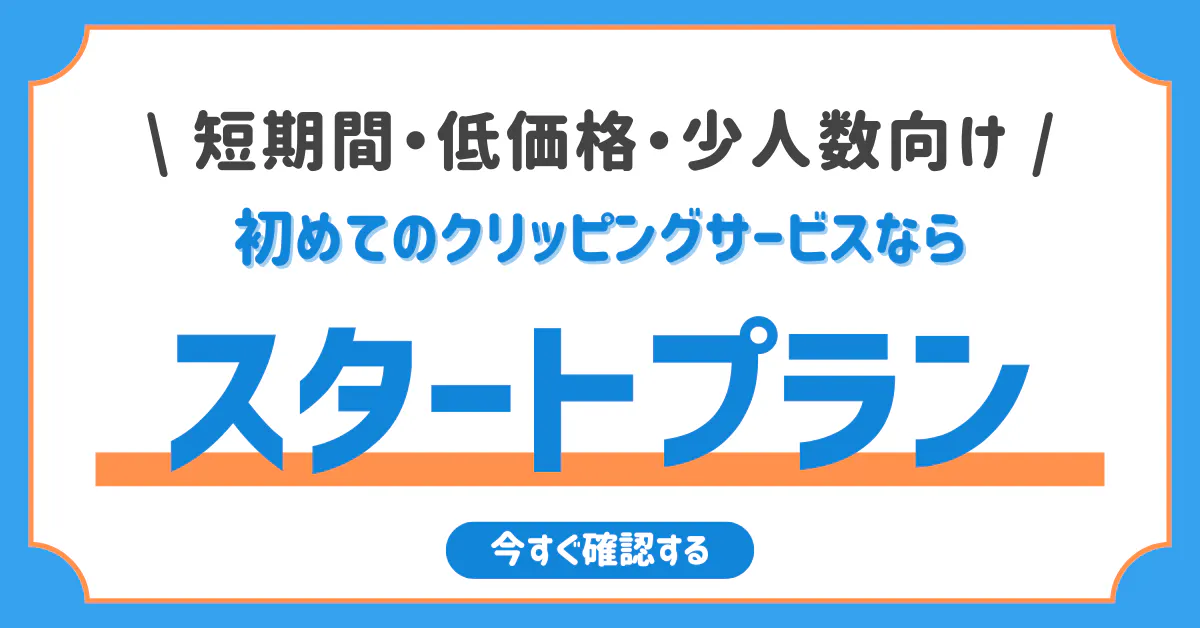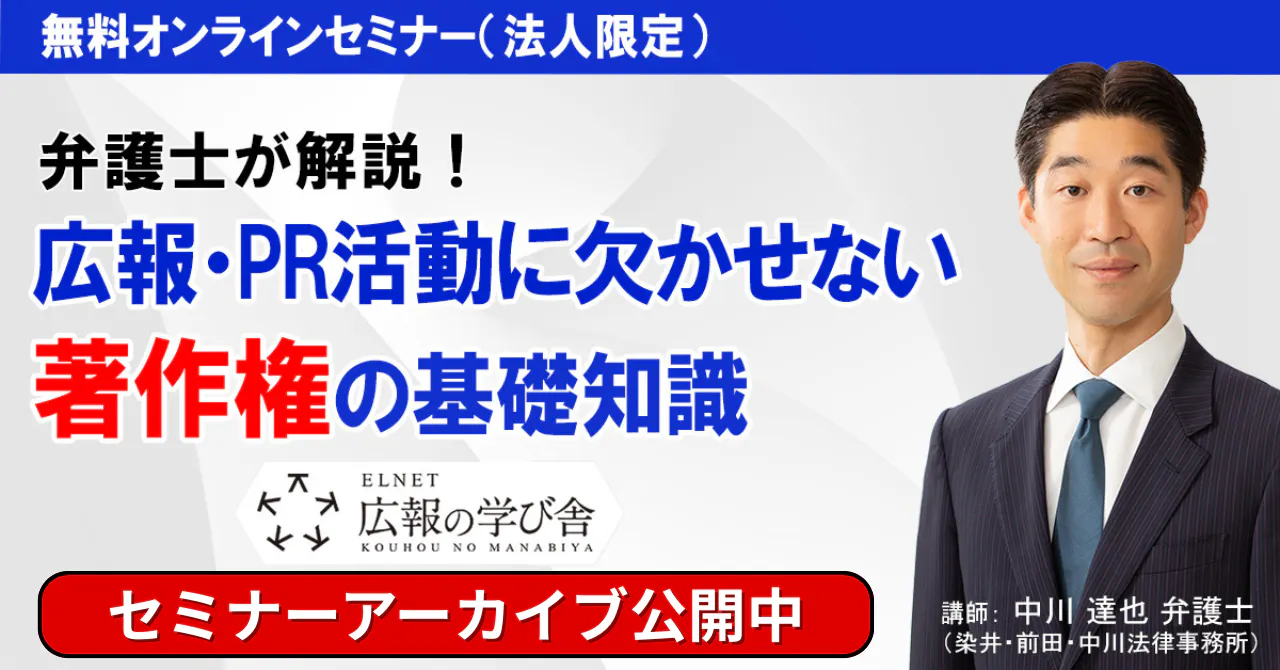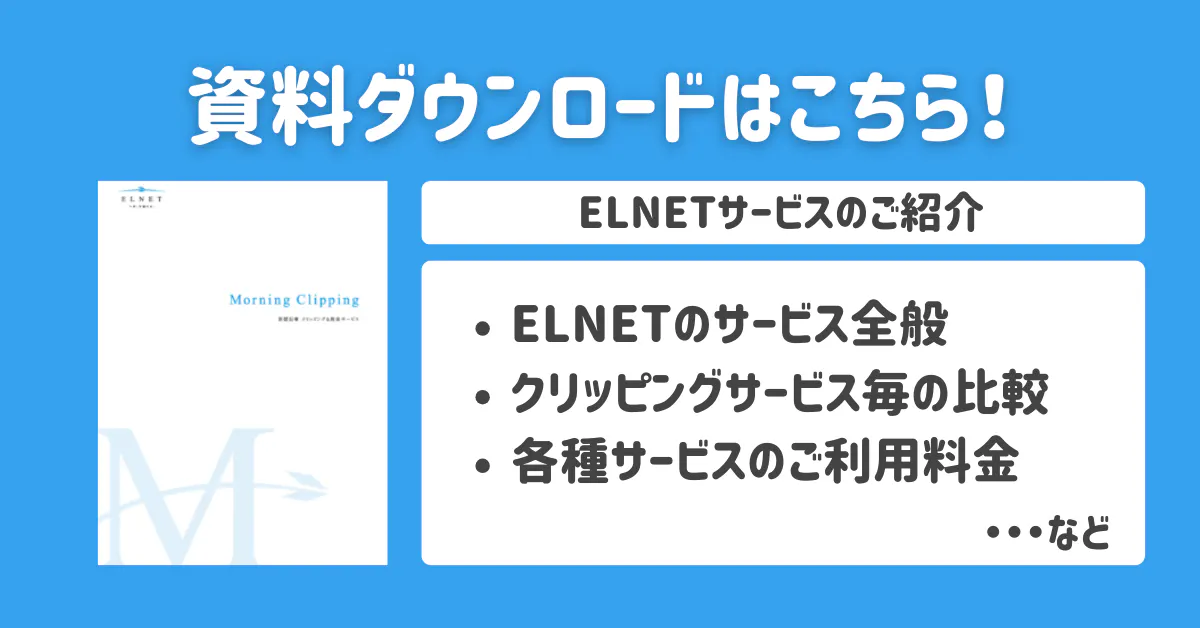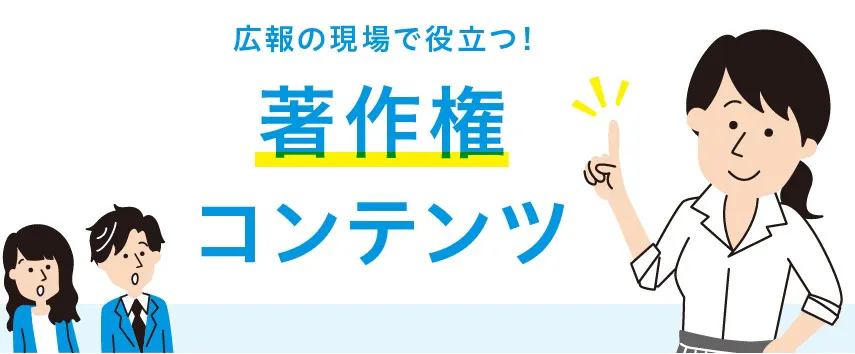【ELspot+】~特別講演会~危機管理広報[後編]-2024.07.24-

【本日の流れ】
- 講演会:『危機管理広報について』 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授 山口 真一氏
- Elspot+について(ELNET営業部 部長 佐藤 宏之)
- グループディスカッション:『危機管理広報について』(①7月11日 ②7月24日)
- 参加者の感想
以下よりぜひお読みください!
「危機管理広報」というテーマで行われた第13回ELspot+交流勉強会。
【前編】では7月11日の様子をご紹介しましたが、【後編】では7月24日に同じテーマ・内容で行われた交流勉強会をご紹介します。
参加メンバーが異なるため、議論の視点や気づきの内容もやや違い、全体としてより幅が広がりました。【前編】と合わせてお読みください。(交流勉強会は同一テーマ・内容で毎月2回開催されます。参加する方は都合の良い日程を選んで参加することができます)
3.グループディスカッション(7/24):「危機管理広報」
講演会に引き続き、グループに分かれて「危機管理広報」についてのディスカッションが行われました。ディスカッションでは、次のような気づきやコメントがありました。
危機管理マニュアル、ガイドラインを作りっぱなしにしない
● 危機管理マニュアルは作成してあるものの、そのままになっている。他社では、年1回の研修や想定トレーニングを行ったり、定期的に見直したりしていると聞いた。持ち帰って、検討したい。
危機管理の必要性を、どうやって社内に浸透するか
● 危機管理マニュアルやガイドラインは作成するだけでなく、それをいかに社内に浸透させるかが大事。そのためには、内容を伝えるだけでなく、どういう影響があるのか(株価下落の危険性など)の実例を伝える必要があると思った。
広報だけで対応するのではなく、他部署との連携も必要
● 炎上が起きた時には、広報だけでは対応できない。日頃から、危機が起きた場合を想定して、他部署を巻き込んだフォーメーションや対応窓口を決めておくことが重要。
● 危機管理マニュアルを作成する際には、広報だけで作るのではなく、他の部署(法務部、リスク管理部門)や第三者(ステークホルダー)に確認しながら、連携して作成することが重要。
その他、こんな意見やコメントもありました
● 危機管理マニュアルがあれば「想定内」のことにはある程度対処できるが、問題は「想定外」のことが起きた時にどう対処するか…。他社の先行事例を蓄積し共有することで、「想定外」のことが起きた時の対応に活かしていくことが重要だと思った。
4.参加者の感想
最後に、交流勉強会に参加した感想をうかがいました。皆さんからは次のような感想がありました。
⮚ 講演会「危機管理広報について」は、実際の炎上事例やその原因、また、炎上した際の対処方法を、実例とデータに基づきながら具体的に紹介・解説いただき、非常に参考になりました。とても中身の凝縮されている講演内容でした。
⮚ 他社での取り組み事例と課題を聞くことができ、自社の危機管理マニュアルを作成・活用するための具体的なイメージが浮かんできました。
⮚ 他社の具体的な取り組み事例を聞くことができました。「うちではできていないな」ということや、「それなら自社でもできそうだ」ということも多く見つかり、有意義な時間でした。早速、社内で検討してみたいと思います。
⮚ 講演会とディスカッションを通して、危機管理の実例や各社の具体的な取り組み状況を交換できて、自社で見落としていた観点を学べました。
⮚ 他業界の広報の話を聞くことで、日頃の自分とは違う感覚で「広報」を捉えることができました。
⮚ 他社の広報の方と交流でき、日頃の悩みや思っていることを聞いてもらえました。普段一人で考えていることを話せて、とても良い機会でした。