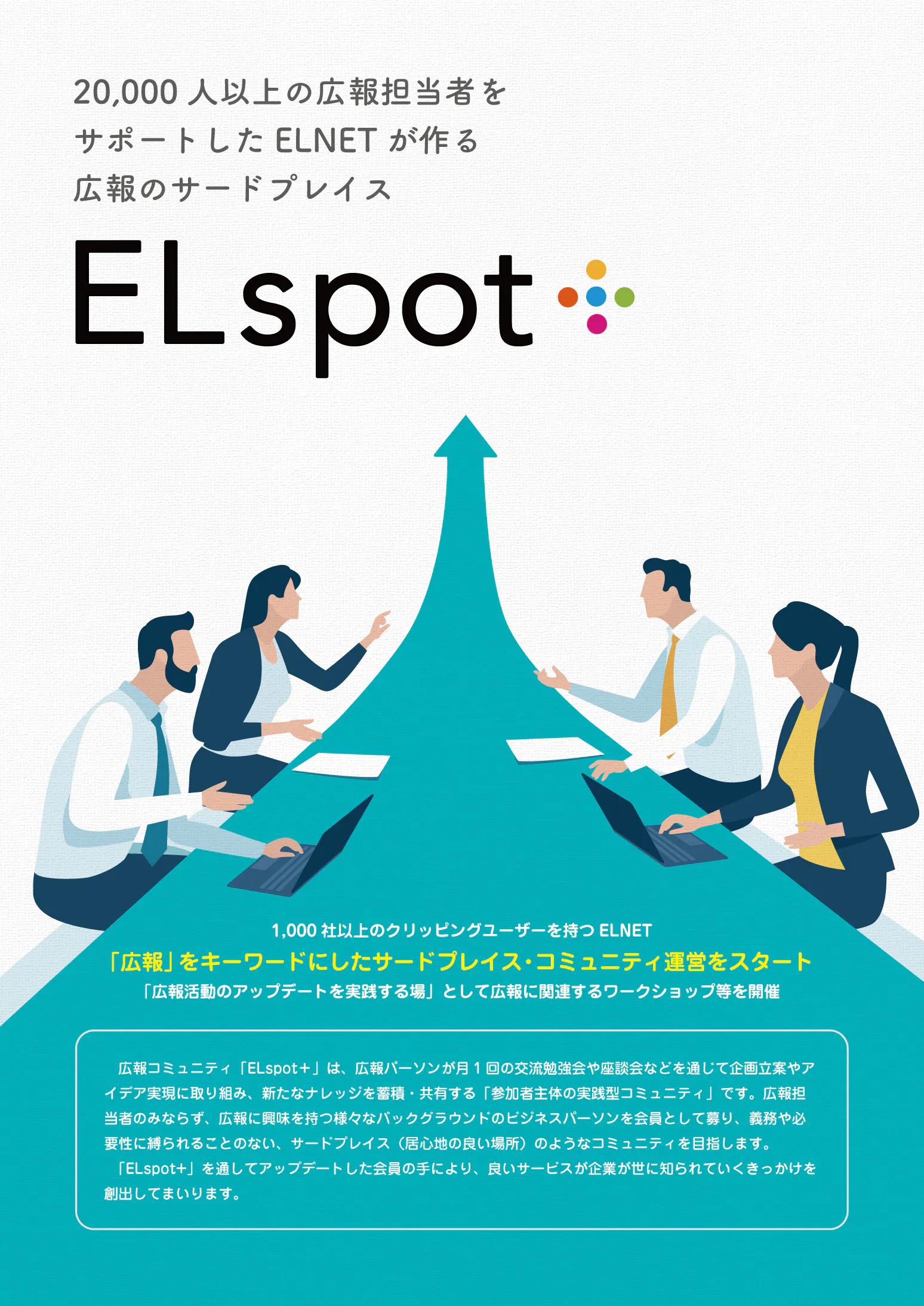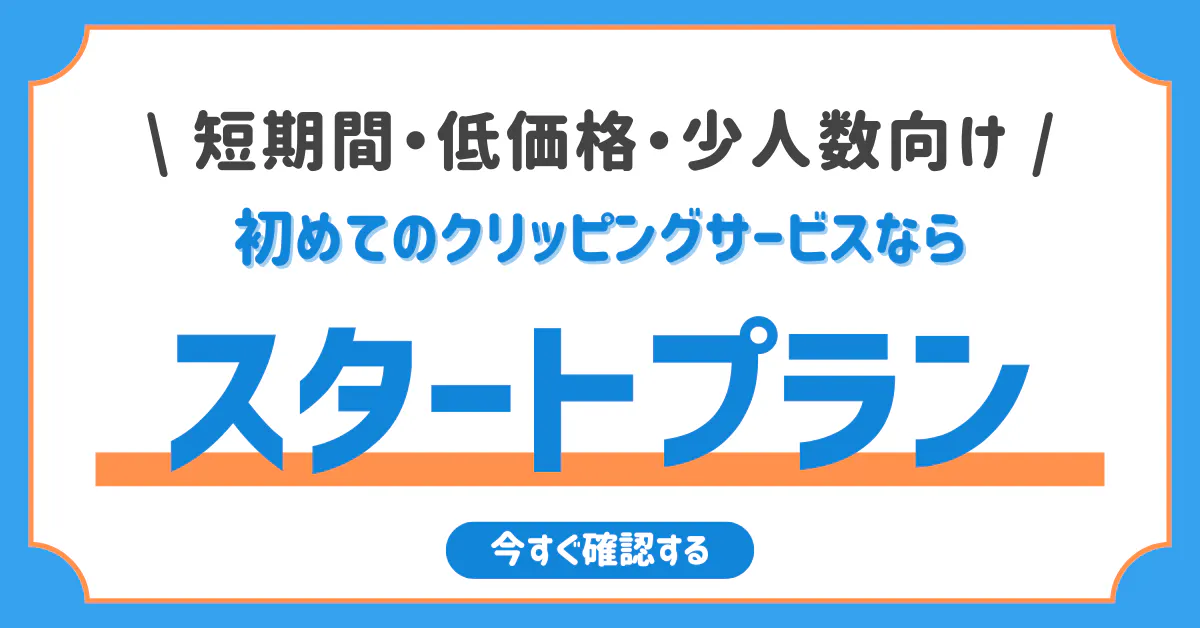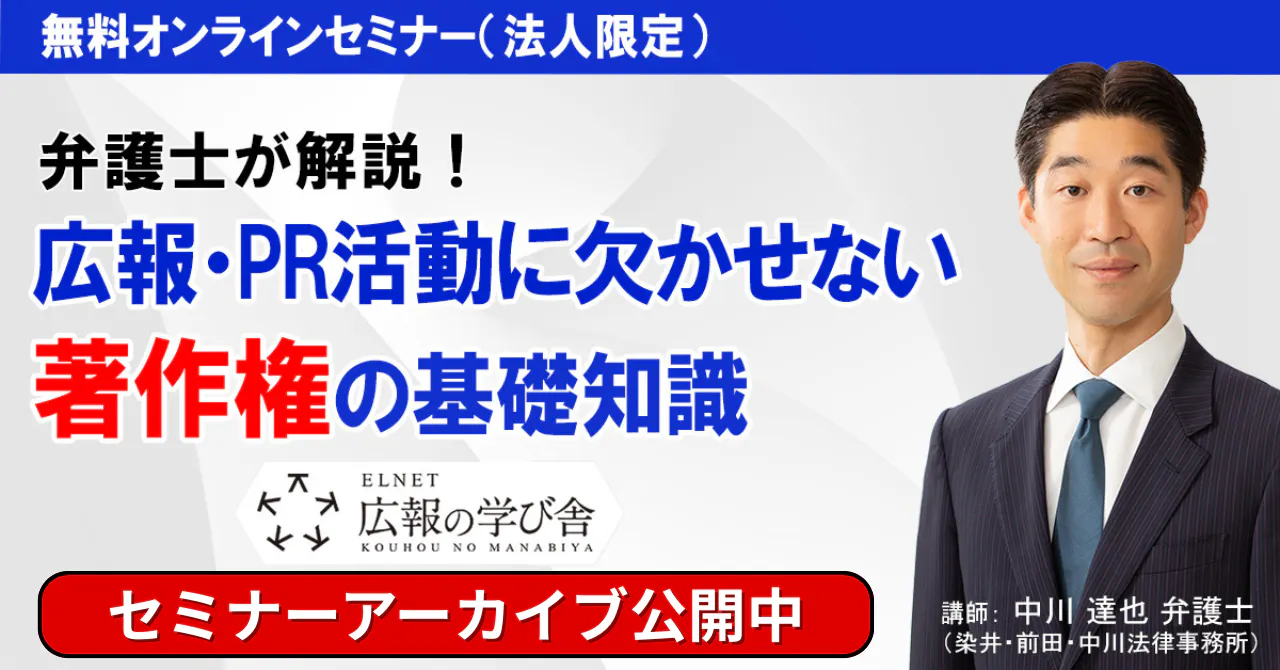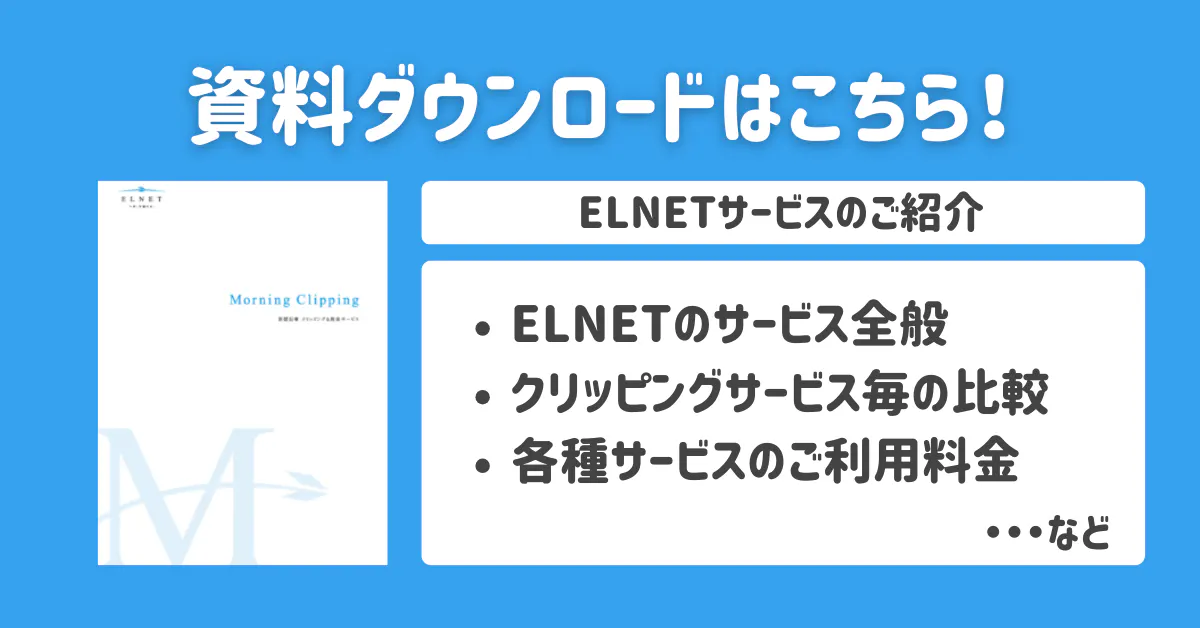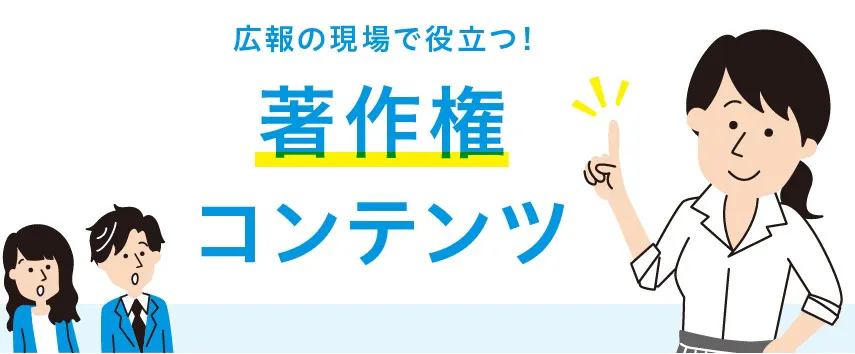【ELspot+】メディアアプローチ~自社を取り上げてもらうために注力していることは?~[前編] ‐2024.05.16‐

本日の流れ
- ELspot+で大事にしていること(ELNET営業部 部長 佐藤 宏之)
- 参加者の自己紹介
- 『自社を取り上げてもらうために注力していること ~私が心がけていること、大切にしていること~』 株式会社U-NEXT HOLDINGS ブランド・コミュニケーション統括部広報部長 滝口 未来 氏
- グループディスカッション『自社を取り上げてもらうために注力していることは?』 ①5月16日
自社を取り上げてもらうために、メディアにどのようなアプローチをしていますか?
――「メディアアプローチ」は広報活動において基本中の基本です。でも、それだけに、「じつは、どこから手をつけていいのかわからない」「従来からのやり方でやっているけど、最近、効果が出にくくなった」「時代の変化に合った新しいアプローチはないものか」…など、広報担当者としての課題や悩みも多いのではないでしょうか。雑誌『広報会議』の2024年5月号でも、「メディア取材が増える広報の秘訣」が特集されています。また、Elspot+交流勉強会の参加者アンケートでも、4人に1人の人が、「メディアアプローチをテーマにしたい」と考えているようです。
そこで今回は、「メディアアプローチ」について、レクチャーとディスカッションを通して考えました。本レポートでは、前編と後編に分け、前編ではレクチャー内容とディスカッションの一部をご紹介します。
1)ELspot+で大事にしていること
ELspot+交流勉強会では、参加者の方一人ひとりが「アウトプット」することを大事にしています。
皆さんが、各回のテーマについての情報を「インプット」するだけでなく、この場でインプットやディスカッションしたことを、会社の中で誰かに説明したり、実際に活用できるように応用していただければ、と思います。
そういう場を、皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。
3)『自社を取り上げてもらうために注力していること~心がけていること、大切にしていること~』
(株式会社U-NEXT HOLDINGS 広報部長 滝口未来 氏)
今回のテーマに関するレクチャーとして、株式会社U-NEXT HOLDINGSの広報部長・滝口未来さんより、「自社を取り上げてもらうために、注力していること」と題して、ご自身が日頃から心がけ、大切にしている5つのポイントについて、お話しいただきました。
【大切にしていること】
①:世の中の流れや会社の状況にあわせた広報活動
「私が広報を立ち上げた頃(2012年頃)は、当社は知名度がある状態ではございませんでした。ですから、とにかく記者さんにアタックすることから始めました。まずは、自社が置かれた状況や規模、認知度などに応じた広報活動が重要だと思います」
②:人との交流(社外・社内all)、ご縁を大切に
「広報で一番大事なのは信頼です。信頼は人との交流から生まれます。私の場合、他社の広報の知人から紹介してもらった記者さんに、とても良い記事を書いてもらったことがあります。こういった勉強会などの場で、他社の広報の方と知り合いになることは、とても有意義なことだと思います」
③:即レスはマスト!24時間ルール
「私たちがお付き合いする記者さんや経営者の方は、皆、多忙なため、スピード感を大切にされています。なので、何か連絡や依頼をいただいたら、できるかできないかはさておき、まずは24時間以内にレスポンスすること。そして、『頼れるな』と思ってもらえれば、仕事がうまくいきます」
④:継続は力なり とにかく続ける
「広報の仕事は、すぐに結果がでないのが辛いところ。でも、それが面白いポイントでもあります。私の場合、7年かけてようやく結果が出たこともあります。お付き合いを続けていれば、いつかはチャンスがくる。続けていれば、いつかは実るものです」
⑤:経営陣との対話
「経営陣の思いや考えをアウトプットするのが広報の仕事。時に、経営陣と記者さんとの間でサンドイッチ状態になることもありますよね。経営陣も記者さんも人間ですから、両者がどんな性格なのかを知っておくことも大事です。両者の特徴や相性が分かると、広報の質も上がります」
さいごに一言
「広報は、お金ではなく、信頼が価値になる仕事です。とても面白く、やりがいがあり、私は大好きな仕事です」
4)グループディスカッション「自社を取り上げてもらうために注力していることは?」
①5月16日
後半のディスカッションでは、5つのグループに分かれ、「自社ではどんなメディアアプローチに注力しているか?」「その効果はどうだったか?」「そこから見えてきた課題と改善策は?」などについて話し合いました。ディスカッションを通して、次のような情報共有や新たな気づきがありました。
メディアとの「リアルな交流の場」を、積極的につくっている
- 経営者とメディアとのリアルな接触の場(イベントや懇親会、会食)を積極的に作っている。
- 記者との懇親会は、メディアへの情報発信(アウトプット)の場としてだけでなく、業界トレンドや経済動向、市場動向の「インプット」の場としている。そこで得た情報を社内に持ち帰って、経営陣と対話し、次の広報戦略を考える材料にしている。
- 記者向けの勉強会を開催している。自社の事業説明だけでなく、広く業界動向や調査結果の報告などを行っている。
メディアにアプローチするだけでなく、アプローチ後の結果分析を重視している
- 効果的な広報をするために、配信した後にどれだけ見てくれたのかの結果を分析している。その上で、分析結果に基づいたPDCAの計画を立てている。
- リリースが記事にならなかった時に、「なぜ、その情報が取り上げられなかったのか」の理由を聞くことが重要。
プレスリリース以外の情報発信を積極的に行っている
- 商品などのプレスリリースだけでなく、一定期間ごとの自社の動向をまとめた「コラム」をメールで送っている。
- プレスリリースにまではなっていないが、それ以前の段階でも「企画書」として持っていくこともある。
取引会社や関係会社など、他社との連名リリースを積極的に行っている
- 自社だけではインパクトが弱い場合は、取引先との連名でのリリースを出している。その方が記事としてもインパクトがあり、結構、取り上げてくれることが多い。
記者さんには、「情報」だけでなく、「気持ち」を伝えるように心がけている
- 自分たちが「書いてもらいたい」情報を伝えるだけではなく、「なぜ、書いてもらいたいのか」という気持ちを伝えることが大事だと思う。
広告を出しているメディアとの良好な関係をつくっている
- 広告を出しているメディアと良い関係性をつくって、さりげなく、「こういう記事を書いてくれませんか?」というアプローチをすることもある。
記事の内容やタイミングについて、メディア側の事情や思惑を知るようにしている
- メディア側(テレビや雑誌はとくに)にも、どういう情報をどういう時期に載せたいか、というタイミング(テーマごとの旬)がある。それを掴んでおくことが重要。
その他、今回のテーマとは別に、こんな意見や気づき、情報共有がありました
広報には「社内風土」を変える力がある
- ある時、「女性活躍」に絞った内容を集中的に広報することで、結果として、社内の風土を変えることができた。広報には、会社の風土を変える力があることを実感した。
社内での広報プライオリティを上げるためにしていること
- 広報活動のPDCA、KPIを経営陣と共有し、記事の掲載状況、掲載結果の分析、振り返りを、定期的に経営者に伝えている。
- 事業部ごとに広報窓口を決めて、定期的に情報収集・共有を行っている。
……ディスカッションでの気づきはまだまだ続きます。後編では5月29日に行われた回でのディスカッション内容と、参加された方々の感想をご紹介します。
以上